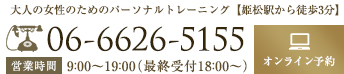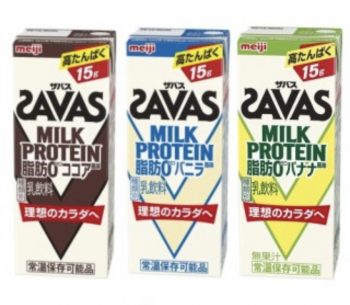「気分が落ち込む。」更年期症状に悩む女性には筋トレがベスト
今日は筋トレのメンタルへの影響について書いていきます。
日本人は精神的なストレスに弱いと言われています。
なかでも45〜50歳代の女性は、更年期の影響で精神が不安定になりやすいと言われています。
更年期症状がでるメカニズムを簡単に説明
❶女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少
❷視床下部:ホルモン分泌の命令を出す所
「命令したのになんでエストロゲンでてないんや。もっと出させろ‼︎」と視床下部が命令を強め混乱する。
❸視床下部は自律神経の調節も担っているため、自律神経も混乱し様々な症状がでる。
その一つが気分の落ち込みや不安感といった精神的な症状です。この時期は、それまでの時期と比べ14倍も「うつ病」を発症しやすいというデータもあります。
・急に不安になって落ち込んだり
・ちょっとしたことでイライラしたり
身体症状がでる辛さも重なり精神的に参ってしまいます。
気分が落ち込み、何をするにも億劫に。
→体のたるみ・衰えは気になるのに運動する気にもならず、ダラダラしてしまう。
→罪悪感を感じて、自分に自信がもてなくなる。さらに気分が落ち込む。という悪循環に陥ります。
このような悪循環を断ち切るためには、色々な方法がありますが、なかでも特に有効だと思うのは「筋トレ」です。
これには【ドーパミン】というやる気ホルモンが関係しています。聞いたことありますか?
ドーパミンは、気持ちが良いという快楽の他、やる気を高めポジティブ思考に変えてくれます。
筋トレなどのしっかりとした運動をした後、こんな経験ありません?
「ぼんやりしてた頭がなんかスッキリした。」
「爽快感、達成感があって気分が良い。」
ドーパミンは、目標をクリア(小さな目標でOK)したり、なにかをやりきった時に分泌が増えます。
まさに筋トレ後ですよね。ポジティブ思考、やる気を引き出すのに最適だと思います。
さらに、筋トレは幸せホルモンと言われる【セロトニン】の分泌も促すと言われています。
また、更年期の「気分の落ち込み」などの精神の症状は、セロトニンやドーパミンの分泌の乱れも関係していると言われています。
筋トレを行うことで、セロトニンやドーパミンの分泌が増え、前向きな気持ちになって、幸せも感じられる。
それに、体力アップや引き締めといった体の変化により自信がつく。頑張れる自分に対して自己肯定感が得られる。
実際に「筋トレには不安を解消する効果がある。」という研究データがあります。
前に俳優の武田真治さんも「筋トレが精神を安定させてくれる。」と言ってました。